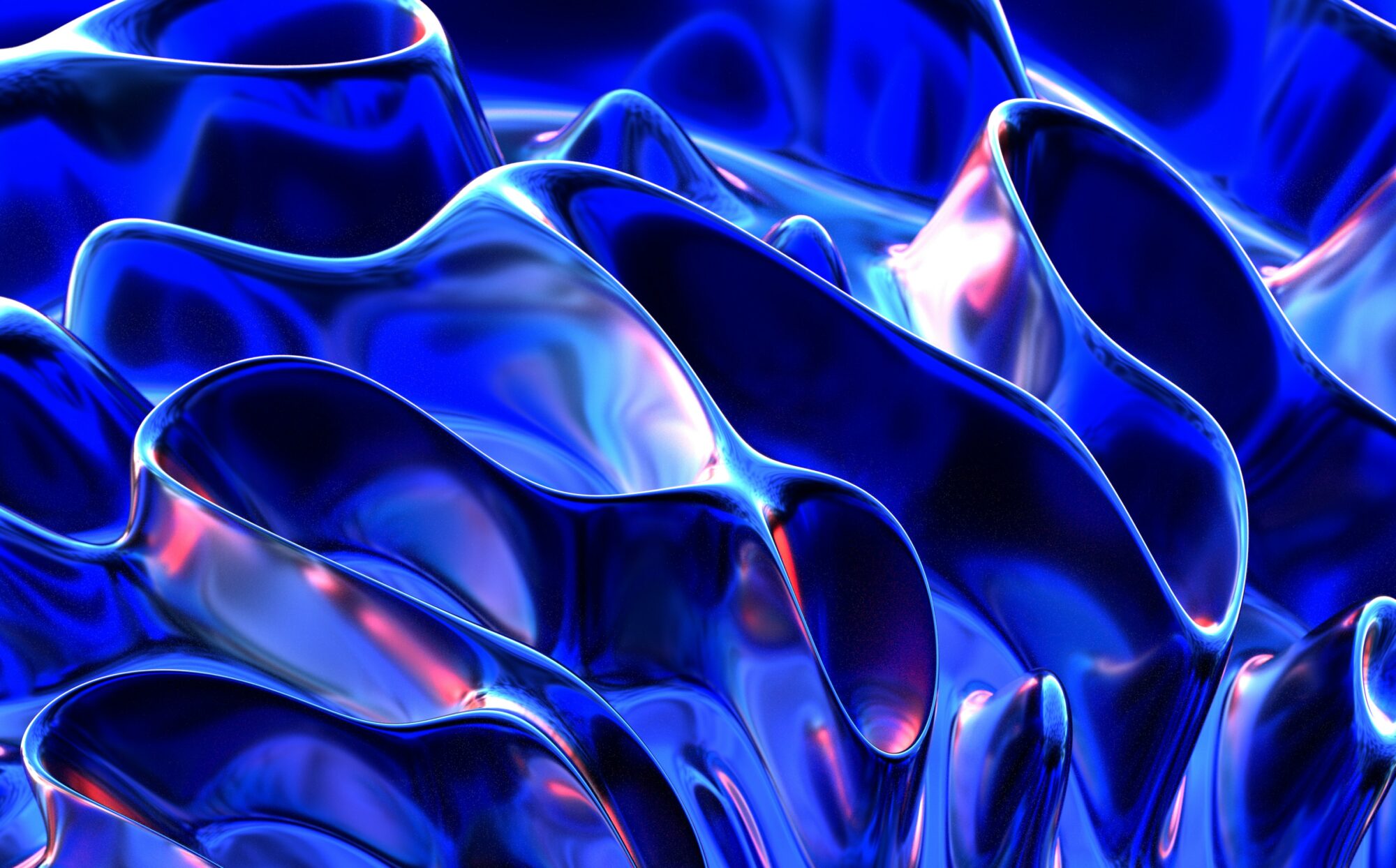リード獲得や短期施策の強化に取り組みながらも、「広報・ブランディングの視点を入れた設計が必要ではないか」
そんな課題意識が徐々に多くのIT企業で高まりつつあります。
本シリーズではこれまで、
- 第1回「短期成果では築けない“積み上がる広報”」の思考を、
- 第2回「語るべきはプロダクト以上の“3つの軸”」という発信の深さを、提案してきました。
そして今回の第3回では、いよいよ「明日からの実践」に向けたチェックリストと、社内で取り組みを推進するためのステップを解説します。
戦略と現場のズレを埋めながら、継続可能なブランド構築を始めるために。
“理想論”で終わらせない中長期ブランディングの、最初の一歩をご提案します。
【この記事でわかること】
- 中長期ブランディングを“絵に描いた餅”で終わらせないために
- IT企業にとって現実的かつ実践的なスタートラインとは?
- 広報・PRを“積み上げ型の設計”に変える5つの視点
- 社内の巻き込み方と、無理なく続ける仕組みのヒント
- すぐに活用できるセルフチェックリストつき(文末)
1. 「なぜ広報するのか?」──目的の言語化がすべての設計の起点になる
中長期ブランディングの最初のつまずきは、“なぜ広報するのか”が明確でないまま進めてしまうことです。
「なんとなく知ってもらいたい」「露出があると安心される」──
こうした曖昧な目的は、組織の中で広報を“飾り”や“あった方がいいもの”にとどめてしまいます。
ここで重要なのは、広報の目的を「ステークホルダー単位」で具体化することです。
たとえば:
- 新規商談の質向上:意思決定者層に対して信頼感を育てる
- 採用:候補者に“共感”される企業ストーリーを発信する
- 提携:潜在パートナーに企業姿勢を届け、初動ハードルを下げる
これは、PR研究におけるステークホルダー理論(Freeman, 1984)にも基づく視点です。
まずは、「何のために」「誰に向けて」広報するのかを一枚の紙に書き出すこと。
これが広報・PRを“積み上がる戦略”に変える最初のチェックポイントです。
2. 自社の“語れる素材”を可視化しているか?
IT企業では「技術で語る文化」が強く、“プロダクト開発の思想”や“判断の背景”といった人間的な側面が言語化されていないケースが多くあります。
しかし、プロダクトが似通ってきた今、「仕様」ではなく「姿勢」で選ばれる時代です。
SECIモデル(野中郁次郎, 1995)にあるように、「暗黙知(個人の経験)」を「形式知(共有できる情報)」に変換することが重要です。
たとえば:
- 開発の裏側で「何をあえて捨てたのか」
- UI改善の会議で交わされた葛藤
- 顧客のひとことに自社の哲学が揺れた瞬間
こうした物語は、社外の共感や信頼を呼ぶ最も強いメッセージになります。
「自社が“他社より語れる”ことを10個書き出す」──これが発信の軸づくりの第一歩です。
3. 「いつでも出せる状態」になっているか?──広報資料の整備チェック
広報資料が整っていないと、せっかくのメディア依頼や取材チャンスも活かせません。
とくにIT企業では、プロダクト開発優先で「対外的な語りの素材」が後回しになりがちです。
必要な土台資料の例:
- 会社紹介文(100字/300字/600字)
- 代表者プロフィール(略歴+価値観)
- メッセージや理念の文章化
- 写真やイメージ素材(人物/製品/オフィス)
「IR」「採用」「営業」など他資料との整合も意識しながら、“すぐに渡せる状態”に整えることが、広報スピードを加速させます。
4. “広報を継続できる仕組み”を設計しているか?
広報は“やること”より“続けること”のほうがはるかに難しい。
IT企業に多い「リソース集中型」の体制では、担当者依存/キャンペーン依存で止まりやすくなります。
習慣化の工夫例:
- 月1本のnote発信を部門ローテで執筆
- 発信テンプレートの共有(タイトル・導入文構造など)
- Slackで「今週伝えたいこと」を週次投稿
- KPIを“発信したか”で評価するルール化
広報の定着は“気合”ではなく“設計”で決まります。
継続できる体制づくりが、企業の語りを資産に変えていきます。
5. 「定期的に見直す場」が設けられているか?
広報とは、企業の“語りの精度”を高め続ける営みです。
IT企業はプロダクトの進化が早く、語るべき内容が更新されているにもかかわらず、発信が追いつかないまま放置されがちです。
おすすめの問いかけ:
- 「この3ヶ月で、伝えていることにズレはないか?」
- 「競合と比較して、自社の語りは差別化されているか?」
- 「ユーザー・パートナー・採用候補者からどう見えているか?」
このような振り返りの時間が、広報を“点”ではなく“流れ”に変えていきます。
まとめ
- 広報の設計は、「誰のために、なぜ発信するのか」という目的の言語化がスタート地点
- 自社に眠る語れる資産を発掘・再編集することで、戦略的な発信軸ができる
- 「いつでも出せる資料」と「続けられる仕組み」が、広報のスピードを決める
- 成果よりも、“振り返る習慣”が企業ブランドを成熟させていく
セルフチェックリスト
- □ 広報の目的が、社内で明確に言語化されている
- □ “他社と違う語り”が社内で整理・共有されている
- □ 対外発信に使える資料がすぐに取り出せる状態にある
- □ 広報が「仕組み」として継続されている
- □ 定期的な“発信の見直し”が行われている
すべてにチェックがつく状態が、“積み上がる広報”のスタートラインです。
「社内を巻き込める広報設計をしたい」方へ
「やる必要は感じている。でも、どこから始めたらいいのか分からない」
「代理店には頼ってきたが、次は“社内で育てる広報”を設計したい」
そのような企業・ご担当者のために、Malenでは
“今ある情報・状況”から始められる中長期ブランディング設計のご相談を承っています。
IT企業こそ、技術と言葉が分離しがちだからこそ、伴走する設計パートナーが必要です。